唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。
このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。
「A事業に投資すべきか、それともB事業に投資すべきか…」
「長年貢献してくれた幹部だが、役職を解くべきか…」
「価格を上げるべきか、据え置くべきか…」
経営者であるあなたの毎日は、大小様々な「決断」の連続です。その一つひとつの決断が、会社の未来を左右します。その重圧に、たった一人で向き合い、眠れない夜を過ごした経験が一度ならずあるのではないでしょうか?
経営コンサルタントとして多くの経営者と伴走する中で、私は一つの明確な事実に気づきました。それは、決断が早い社長と、決断に時間がかかる社長とでは、「才能」や「知識量」に本質的な差はないということです。
では、両者を分ける決定的な違いは何か?
それは、「悩む」ことに時間を使っているか、「考える」ことに時間を使っているか、ただそれだけなのです。
このコラムは、小手先のテクニック集ではありません。私が現場で確信した、決断の「本質」をお伝えするものです。最後までお読みいただければ、あなたは「悩み」という名の霧の中から抜け出し、自社の未来を的確かつ迅速に選び取るための「揺るぎない羅針盤」を手に入れることができるはずです。




決断の9割は「悩み」でできている ― 今すぐ「考える」に切り替える技術


決断が遅れてしまう根本原因、それは「能力不足」や「情報不足」ではありません。ほとんどの場合、私たちが無意識のうちに「悩んでいる」状態に陥っていることに起因します。
「考える」と「悩む」の決定的な違い
まず、この2つの言葉を明確に区別しましょう。両者の最も大きな違いは、その行動の「前提」にあります。
- 「考える」とは:「答えは必ず出る」という前提に立ち、結論を導き出すために建設的に思考を組み立てる論理的なプロセスです。
- 「悩む」とは:「答えは出ないかもしれない」という前提で、同じ思考を堂々巡りさせている感情的な状態です。
決断が早い人は、「悩む」という状態を即座に断ち切り、「考える」というプロセスに移行します。では、どうすれば良いのでしょうか。
ステップ1:まず「悩んでいる自分」に気づく
何よりも重要なのは、「今、自分は悩んでいるな」と客観的に気づくことです。一つの目安として、10分以上考えても、具体的な次の一歩が見えてこないのであれば、それは「考え」ではなく「悩み」に陥っている可能性が高いでしょう。まずはペンを置き、一度思考をリセットしてください。
ステップ2:「コントロール可能なこと」だけにフォーカスする
「悩み」から「考え」へ切り替えるための、最も強力なスイッチがあります。それは、以下の問いを自分に投げかけることです。
「この状況で、自分がコントロールできることは何か?」
「悩み」の正体は、そのほとんどが「自分ではコントロールできないこと」に心を囚われている状態です。
- 「景気が悪化したらどうしよう…」(コントロール不能)
- 「従業員はどう思うだろうか…」(他人の気持ちはコントロール不能)
- 「競合が値下げをしてきたら…」(他社の戦略はコントロール不能)
これらは知っておくべき情報ではありますが、それ自体を嘆いていても一ミリも状況は好転しません。それは思考が停止している状態です。優れた経営者は、コントロール不能なことを前提条件として受け入れた上で、「では、自分たちがコントロールできる範囲で、最善の一手は何か?」と問いを立てます。
例えば、業績悪化に直面した時、
- 悩む人:「市場が縮小しているからダメだ…」
- 考える人:「市場が縮小する中で、まだ開拓できていないニッチ市場はどこか?」「既存顧客への提供価値を高めるために、今すぐできることは何か?」
このように、「コントロールできること」に焦点を合わせた瞬間、あなたは「悩み」の状態から抜け出し、具体的な答えを導き出す「考え」のステージに立っているのです。
最強の武器を手に入れる ― 決断の揺るぎない「判断基準」とは?


さて、「コントロールできること」に焦点を合わせると、次なる問いが生まれます。「数ある選択肢の中から、どれを選ぶべきか?」
その解を出すための最強の武器が、経営理念やビジョンという「判断基準」です。「なんだ、そんな綺麗事か…」と思われたでしょうか?もしそう感じたなら、それはあなたの会社の理念が、まだ「額縁の中に飾られたお題目」になっていて機能していない証拠かもしれません。
私が知る優れた経営者たちは、例外なく、この経営理念を「生きた道具」として、日々の決断における唯一無二の憲法として活用しています。
なぜ、理念が決断のスピードと精度を上げるのか
考えてみてください。
- 「我が社は何のために存在するのか?(存在意義)」
- 「どこを目指しているのか?(ビジョン)」
- 「何を大切にするのか?(価値観)」
この問いに対する答えが明確であれば、目の前の選択肢が「理念に合致しているか、していないか」で判断を下すことが可能です。
- 目先の利益は大きいが、理念に反する取引 → やらない
- 短期的には赤字でも、ビジョン実現に不可欠な投資 → やる
- A案もB案も魅力的だが、より我が社の価値観を体現しているのはA案 → A案を選ぶ
このように、判断基準が明確であれば、個人的な感情やその場の雰囲気に流されることなく、一貫性のあるブレのない決断が可能になります。選択肢を前にして「うーん…」と悩む時間が劇的に減り、「我社の理念に照らすと、答えはこれだ」と即座に「判断」できるのです。
「判断基準」を磨き上げる具体的なアクション
もし、あなたの会社の理念が曖昧であったり、社員に浸透していなかったりするならば、今すぐやるべきことは、次の会議の議題を決めることではありません。判断基準そのものを磨き上げることです。
- 理念を言語化する:あなたの頭の中にある想いを、誰が読んでも理解できる、シンプルで力強い言葉に落とし込みましょう。
- 常に立ち返る癖をつける:その理念を手帳の1ページ目に書き、毎日一度は目を通してください。判断に迷った時に「さて、我々の理念に照らすとどうだろう?」と、常に立ち返る癖を社長自身がつけることです。
- あなたの言葉で語り続ける:社員は、壁に貼られた美辞麗句ではなく、社長の口から語られる理念に心を動かされます。あらゆる機会を通じて、決断の背景にある理念をあなたの言葉で語り続けてください。
悩む時間があるなら判断基準を磨く。これが、的確な決断への最短距離です。






「判断基準」を使いこなすための思考整理術
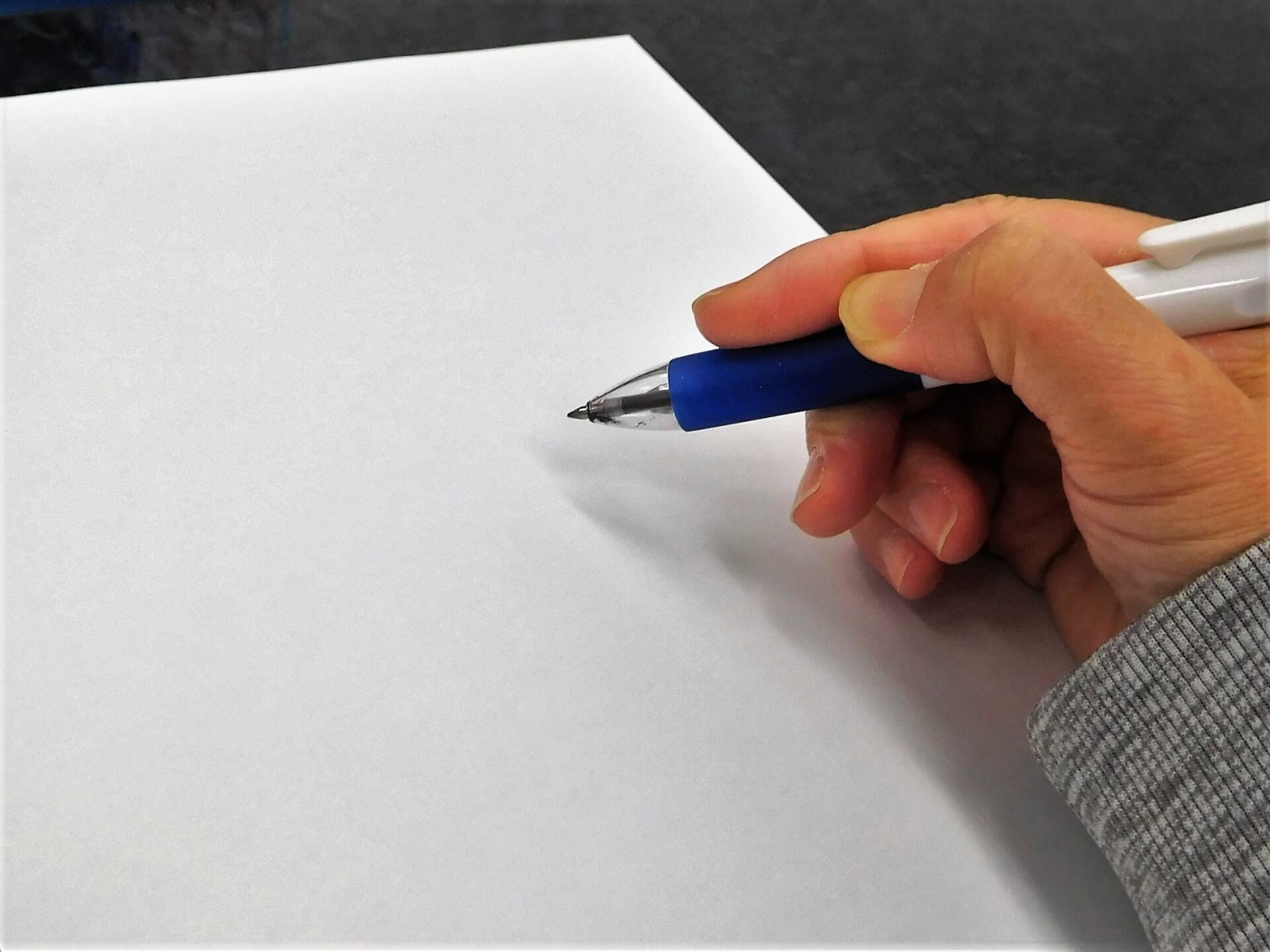
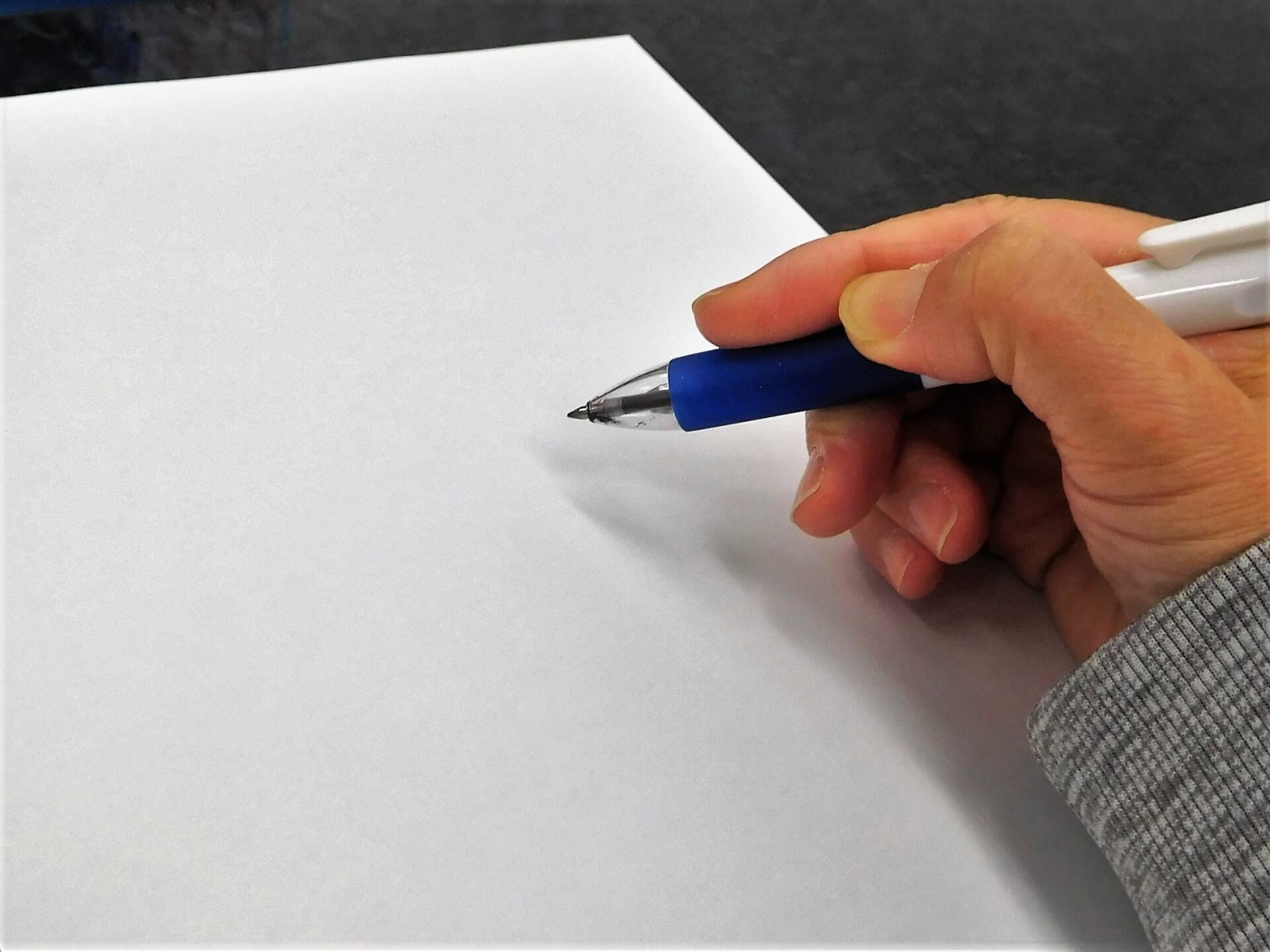
明確な判断基準(理念)を打ち立てたら、次はその基準を目の前の複雑な問題に正しく適用するための技術が必要です。ここでは、シンプルかつ強力な思考整理術をご紹介します。
ステップ0:まず、頭の中をすべて書き出す
考える際、頭の中だけでやろうとしないでください。必ず、紙とペンを用意し、白紙にとにかく書き出すことから始めます。テーマに関する単語、感情、懸念、アイデア、事実…どんな粒度でも、どんな言葉でも構いません。頭に浮かんだものをすべて紙の上に吐き出すのです。
これにより、思考を客観的に眺めることができ、問題の全体像が可視化されます。書き出した要素は後になって線で結んだりグループ化したりするだけで、驚くほど頭が整理されるはずです。
ステップ1:理念を軸にした「プロコン分析」
頭の中が整理されたら、次に「プロコン分析」を行います。プロコン分析とは、「Pros=メリット」と「Cons=デメリット」を書き出し、比較検討する手法です。ポイントは、これを「自社の判断基準(理念)に照らして」行うことです。
<理念を軸にしたプロコン分析の実践ステップ>
- 選択肢を定義する
(例:A案「海外の格安工場に生産移管」、B案「国内工場に設備投資」) - 書き出した要素をメリット・デメリットに分類する
ここで、単なる金銭的な損得だけでなく、「理念に照らしたメリット・デメリット」を考えます。
| A案:海外移管 | B案:国内投資 | |
| メリット (Pros) | ・コスト大幅削減(財務的) ・価格競争力の向上 | ・「高品質」という理念を追求できる(理念的) ・従業員の技術力と士気が向上 ・ブランド価値の向上 |
| デメリット (Cons) | ・「Made in Japanの高品質で貢献する」という理念に反する(理念的) ・技術の空洞化リスク ・国内従業員の雇用問題(価値観との不一致) | ・多額の初期投資が必要(財務的) ・投資回収に時間がかかる |
- 理念を基に判断を下す
上記のように表で比較すれば、答えはより明確になります。短期的な利益を追うならA案かもしれませんが、「高品質」という理念を会社の根幹とするならば、選ぶべきはB案である、という結論に至るでしょう。
思考ツールは、それ自体が答えを出すものではありません。あなたの会社の「判断基準」という光を、問題の核心に正確に当てるための「レンズ」の役割を果たすのです。
判断基準を曇らせないための日常習慣
一度、揺るぎない判断基準を打ち立てても、日々の忙しさの中でその輝きが曇ってしまうことがあります。大切な基準を常にクリアに保ち続けるための習慣をご紹介します。
- 「理念」と「データ」の両輪で走る
理念というコンパスは進むべき「方向」を、そして客観的な「データ」は現在地を示す「海図」です。「熱い理念(想い)」と「冷静なデータ(事実)」。この両輪を回すことで、あなたの決断はより強固なものになります。 - 心身のコンディションを最高の状態に保つ
最高の判断基準を持っていても、それを使う経営者自身が疲弊していては、正しい判断は下せません。社長の仕事は、現場で作業することではなく、「最高のコンディションで、最善の決断を下すこと」です。十分な睡眠、適度な運動。これらは経営者の「義務」だと考えてください。
私の体験談


私が経営コンサルタントとして関わったある企業の話です。
クライアントであるその社長は従業員50名規模の企業を経営し、新規事業の立ち上げを目指していました。しかし、最初の市場調査やリスク分析の段階で、競合リスクや投資の大きさ、内部リソースの制約が浮き彫りとなり、計画は次第に遅れ、気がつけばアイデアを思いついてから1年が経過していたとのことです。
そこで私は、まず社長と一緒に情報収集の方向性を再設定し、意思決定のための具体的な判断基準を一つ一つ明確にしました。また、決断の速度を高めるために、短期間で小さな決断を積み重ねる方法も導入しました。例えば、事業コンセプトのブラッシュアップや市場セグメントの絞り込みといった部分で、私から1つ1つポイントになりそうな部分をピックアップしながら社長に問いかけをし、素早い意思決定を行う訓練を兼ねて、確実に一歩ずつ前進できるサポートを行いました。
このプロセスの中で、社長は少しずつ「情報を集めすぎて動けなくなるリスク」を理解し、現状持っている情報の中でベストな判断を行う重要性を実感するようになりました。そして最終的には、新規事業の具体化に向けて明確な方向性と計画を定め、必要なリソースの手配やパートナーとの協業に向けた準備に踏み出しました。
このように、決断力を鍛えるだけでなく、実際の行動計画を伴走することは、経営者が抱える課題を解決し、企業の成長を促進する強力な手段です。私自身、この支援を通じて、経営者の意思決定がいかに企業の未来を左右するかを改めて実感しました。
Q&A
Q1. 役員会で意見が真っ二つに割れてしまいます。どうすればよいでしょうか?
A. 素晴らしい状況です。それは役員が真剣に会社のことを考えている証拠です。ここで社長がすべきは、多数決ではなく、「そもそも、我が社の理念に照らした時、どちらがより我々の存在意義を体現しているか?」と議論の土俵を一段上げることです。それぞれの意見の根底にある価値観を理念と結びつけて議論させ、最終的には社長が「我が社の理念に基づき、私が責任を持ってこちらを選択する」と宣言してください。
Q2. 重要な決断を前にすると、どうしても不安になります。どうすれば?
A. 不安は責任感の証です。その不安の正体は、「コントロールできない未来」に対する「悩み」です。そんな時こそ、あなたの会社の理念を読み返してください。思考が「答えのない未来」から「答えのある、我々が目指すべき姿」へと引き戻され、個人的な感情から解放されます。拠り所となる理念があることが、どれだけ心強いことか実感できるはずです。
Q3. 情報が不十分な中で、決断を迫られています。どうすれば?
A. ビジネスの世界で、情報が100%揃うことはありえません。情報が不十分な時こそ、判断基準の真価が問われます。競合のデータも、市場の未来予測も不確か。そんな時に唯一信じられるのは、「我々は何者で、どこへ向かうのか」という自社の理念だけです。不確実な状況は、あなたの会社の理念の強さを証明する絶好の機会なのです。
まとめ:決断力は鍛えられる
このコラムを通じて、本当の決断力とは、フレームワークや情報収集能力以前に、まず「悩み」を断ち切り、「考える」技術を身につけること、そしてその上で、自社の存在意義である「経営理念」という揺るぎない判断基準を持つことに尽きるとお伝えしてきました。
目の前の選択肢に「悩む」のは、もうやめにしましょう。それは時間の無駄です。
あなたがすべきは、ただ一つ。
「この状況でコントロールできることは何か?」を自問し、「我が社の理念に照らし、どう判断すべきか?」と考えること
あなたの決断は、未来を創る力です。その尊い決断に、迷いは不要です。あなたの会社の理念こそが、すべての答えを知っています。どうか、その声に耳を澄ませ、確信を持って、会社の未来をその手で選び取ってください。
私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。
経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。


経営者が抱える経営課題に関する
分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。
初回のご相談は1時間無料です。
LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

