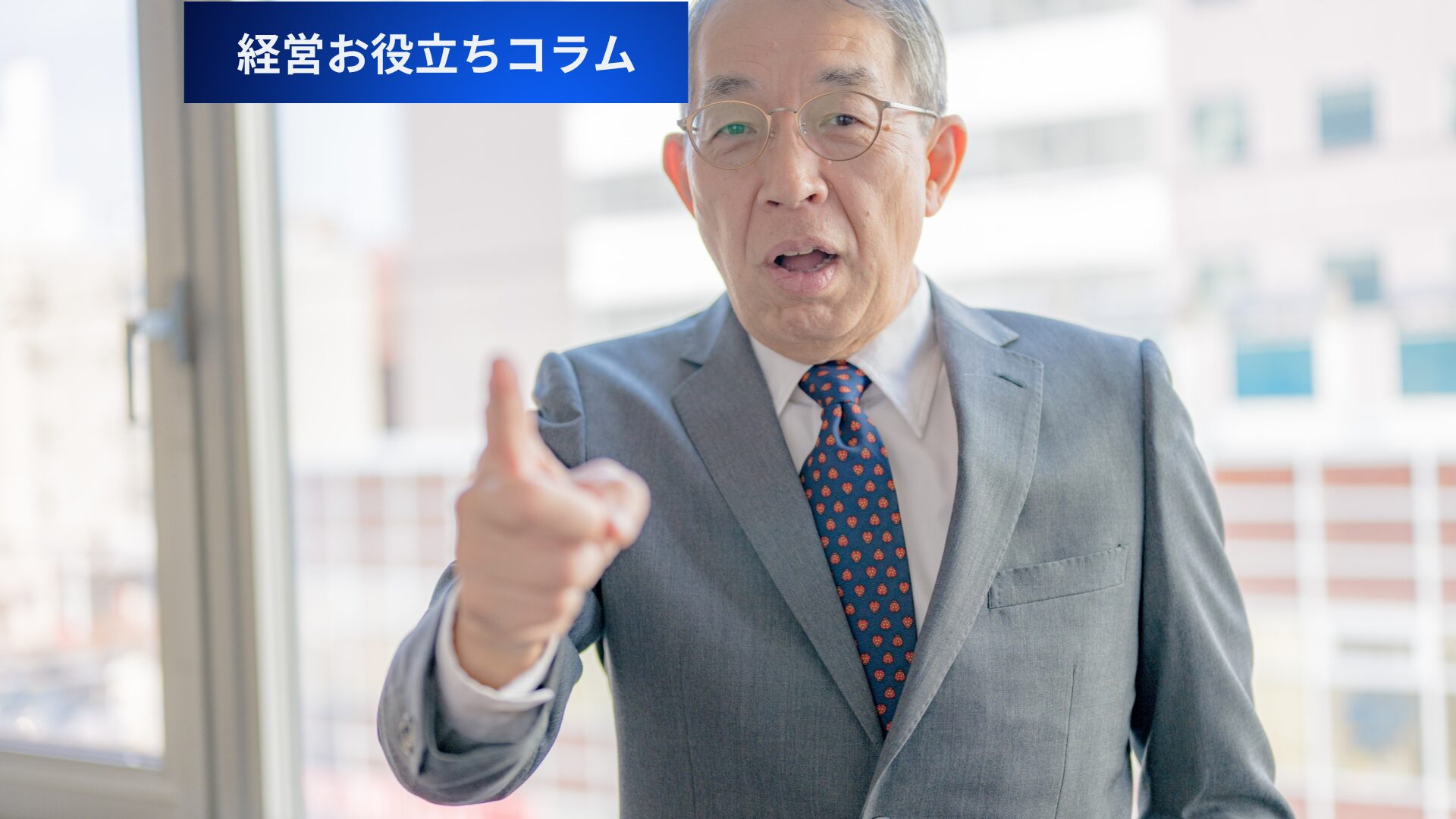唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。
このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。
中堅中小企業の管理職や社員の方々とお話をしていると、「社長が方針をコロコロ変えて、現場は混乱しっぱなしだ」「突然『これをやるぞ!』と指示されたかと思えば、数日後には『やはりやめる』と言われた」という声を聞くことがあります。もちろん、経営環境がめまぐるしく変わる現代においては、柔軟かつ迅速に方針転換を行うことも大切です。
しかし、度を超えた方向転換が繰り返されれば、組織の士気や効率は下がり、最悪の場合「現場が社長についていけない」という状態が生まれてしまいます。
なぜこうした「方針のコロコロ変化」が起こるのでしょうか?そこには単に社長の気まぐれというよりも、「視座の違い」という構造的な問題が潜んでいる場合が少なくありません。経営者が思う「理想像」と、現場の社員や管理職の感じている「リアル」との間に大きなズレが生じているのです。
本稿では、中小企業でしばしば見受けられる「社長が方針をコロコロ変える理由」と、「視座のギャップを埋める方法」について詳しく解説します。 私自身、経営コンサルタントとして20年にわたり数多くの企業様とご一緒させていただき、この問題を解決してきた実績があります。その経験から学んだポイントを余すことなくお伝えしますので、どうぞ最後までお読みいただき、貴社の経営改善・組織力強化にぜひお役立てください。
なお、本記事に関連した内容は音声でも配信していますので、ご興味がある方は以下のリンクよりお聴きください。




社長が方針をコロコロ変える理由


社長が方針を頻繁に変えることについて、現場からは「優柔不断だ」「気まぐれだ」といった厳しい意見が出ることも珍しくありません。しかし、社長ご本人にお話を伺うと「経営環境が変わったから仕方なく変えた」「競合他社が新たな動きを見せたので、こちらも手を打たないと…」といった、ある程度納得感のある理由が出てくる場合も多いものです。
では、なぜ社長は大きな方針から細かい指示まで、短期間で何度も変えてしまうのか?そこにはいくつかの背景要因があります。
変化のスピードと意思決定
現代のビジネス環境は、技術革新や消費者嗜好の変化、また国際情勢の影響など、とにかく動きが速くなっています。大企業であればある程度の経営資源(資金や人員)を使って環境分析ができたり、様々なリスクに備えたりできますが、中堅中小企業では往々にして経営資源が限られており、環境の変化がダイレクトに業績へ影響します。そのため、社長が危機感を抱き、ちょっとした外部情報の変化にも過敏に反応してしまうのは仕方のない面もあります。
しかし、意思決定のスピードを重視するあまり、十分な検討プロセスを省略しがちになり、「あれもやってみよう」「やっぱり違うからこれに変えよう」という流れになってしまうことがあります。社長自身としては「迅速に動いた」と感じているかもしれませんが、現場から見ると「言うことがコロコロ変わる」という印象を受けるのです。
経営環境の変化に対する過度な反応
企業規模が小さいと、新規取引先の一社に左右される売上の比率が大きかったり、主要顧客からのクレームが組織全体に大きなダメージを与えたりしやすくなります。そのため、「このままではまずい」と感じた瞬間にすぐ方針を変え、新しい打ち手を模索し始めるのが中小企業の社長の特徴とも言えます。もちろん、迅速な対処は必要不可欠なのですが、問題の本質を考えずに「その場しのぎ」で方針を立ててしまうと、社員には迷走しているように映りかねません。
経験不足や視座の不足
中堅中小企業の経営者の中には、創業者や同族経営の2代目・3代目の方も多いでしょう。優れたカリスマ性を持ち、一代で大きく成長させたケースも珍しくありません。しかし、場合によっては大企業でのマネジメント経験や体系的な経営に関する知識が不足している場合もあります。
もちろん、経営おいては知識がすべてではありませんが、複雑な課題に直面した際に、ある程度「抽象度の高い視点で状況を捉える力」がないと、どの施策が根本的な解決策になるのかを見極められなくなります。結果として「とりあえず動く」「うまくいかないから別の策を打つ」という流れになりやすく、周囲には方針がコロコロ変わるように映ってしまうのです。
ステークホルダーとのコミュニケーション不足
社長が意思決定を行う場面では、様々な情報が集まってきます。取引先や銀行との関係、社内の声、業界内の動向、さらには個人的な人間関係など。しかし、それらの情報が必ずしも正確だったり、網羅的に把握されていたりするわけではありません。
また、役員や管理職などの主要メンバーとのコミュニケーションが不足していると、経営者が抱えている問題意識や、逆に現場が感じている課題感がすれ違ったままになりがちです。時には「社長が現場の苦労を分かっていない」と言われ、社長からすれば「現場が経営の大局を分かっていない」というジレンマに陥り、結果的に方針がうまく浸透しなくなるのです。
視座のギャップとは?


前章で述べたような背景から「社長が方針をコロコロ変える」状態が生まれますが、その根底には「視座のギャップ」が大きく関わっています。ここでいう「視座」とは、文字どおり「物事を見る位置や角度」を指します。
経営者は会社全体の方向性や将来を見据えて考えますが、現場の社員や管理職は日々の業務や目先の成果に注目せざるを得ません。その結果、視点のズレが生まれ、お互いに理解し合えない状況が形成されるのです。
経営者視座と現場視座
経営者の視座は、企業全体の長期的な成長や、対外的な信頼確保、財務体質の強化など多岐にわたります。一方で、現場視座は、目の前の顧客の要望にどう応えるか、今日のノルマをどう達成するかなど、目先の具体的な課題処理が中心となります。
もちろん、両方とも組織を運営する上で大切です。しかし、中堅中小企業では人員的な余裕が少ないこともあり、どうしても「今この瞬間の業務」で手一杯になりがちです。そのため、経営者の「将来に向けて今のうちにリスク対策を打とう」という言葉は、現場からすれば「まだ起こっていないことを気にかける余裕なんてない」という受け止め方になるかもしれません。
経営の全体戦略と短期的目標のズレ
会社を経営する以上、ビジョンや中長期戦略は欠かせません。一方、現場レベルでは、具体的な売上目標やクレーム対応、新製品の開発・改良など、毎日のように新しいタスクが積み重なります。特に中堅中小企業の場合は、人員や予算の制約があるため、経営者が理想とする「次の成長ステージに向けた大きな投資」と、現場が抱える「今の既存顧客との仕事をきちんとこなさねばならない」という使命感の間には大きなギャップが生じやすいのです。
このようなギャップがあると、経営者は「どうして社員はもっと先を見据えた行動をとらないのか?」と苛立ち、現場は「現状をしっかり固めることが先決なのに、社長が無理ばかり押し付けてくる」と不満を抱きます。結果的に、社長が掲げる戦略が頻繁に変わるように見えたり、社長も「これだと成果が出ない」と感じては新しいアイデアを打ち出し…という負のスパイラルに陥りやすくなります。
多様な利害関係者との距離感
中堅中小企業といえども、経営者が向き合うステークホルダー(利害関係者)は多岐にわたります。取引先や金融機関、株主、行政、さらには従業員や顧客など、すべてが重要な存在です。経営者は各ステークホルダーと対話し、それぞれのニーズを踏まえながら意思決定を行う必要があります。しかし、これら利害関係は時に複雑に絡み合い、社長がどのステークホルダーの声にどこまで配慮するかによって、方針が二転三転することもあるのです。
現場の社員は、取引先や金融機関などと頻繁にやり取りすることが少なく、必ずしも全体の構造を理解できていないことがあります。こうした情報格差が拡大すると、「社長が突然理由もなく方針を変える」という誤解が生じやすくなります。






視座のギャップを埋める具体的なアプローチ


視座のギャップによって引き起こされる「方針のコロコロ変化」は、経営者と現場にとって大きなストレス要因になるだけでなく、企業の成長を阻害する可能性も高いです。では、どうすればこのギャップを埋め、経営者の意図がしっかり伝わり、組織全体が一丸となって走れる状態を作れるのでしょうか?ここでは、具体的なアプローチをいくつかご紹介します。
明確な経営理念と中期計画の策定
まず、重要なのは「企業の存在意義」や「将来どんな企業でありたいか」を明確にし、それを全社的に共有することです。経営理念やビジョンがしっかりと共有されている企業ほど、「なぜ今、この方針転換が必要なのか?」を論理的に説明できる土台が整います。
さらに、中期的な視点(3〜5年程度)での経営計画を作り、それを全社員や主要な幹部と共有することで、社長が出す指示の背景や根拠を理解しやすくなります。例えば「3年後には海外展開を目指すために、今年は英語対応の製品を強化する」といったように、中長期の戦略と現在の具体策を紐づけて示すのです。こうすることで、たとえ経営環境の変化に合わせて短期的に微調整があったとしても、現場からは「突然の思いつきではなく、大きな方向性に沿った判断なのだ」と理解してもらえる可能性が高まります。
経営者のリーダーシップと現場連携の強化
社長が視座を高く持つことは大切ですが、同時に現場のリアリティをどれだけ捉えられるかも非常に重要です。社長が現場に足を運び、社員や管理職との対話を重ねることで、理想と現実のギャップを縮めることができます。
例えば、月に一度は各部署とのミーティングに社長自らが参加する、あるいは現場のキーパーソンと定期的にランチミーティングをするなど、相互理解の仕組みを意図的に作るのです。よく言われることですが、「現場が動く前に、まず社長が動く」。これに尽きます。経営者が強いリーダーシップを発揮しながらも、現場の声を吸い上げ、それを経営判断に反映させる姿勢を示せば、社員たちも経営者の真意を理解し、方針変更の背景を納得しやすくなります。
定期的なミーティングや仕組みづくり
方針転換が頻発する理由のひとつに、「経営者の頭の中の情報が共有されていない」問題があります。頭の中ではある程度筋道が立っているのに、周囲には十分に説明されていないため、結果的に「急に変わった」という印象を与えてしまうのです。これを解消するには、定期的なミーティングや情報共有の場を設けることが有効です。
- 週次/月次ミーティング: 週や月ごとに開催し、経営者が「今どんな情報を得て、どんな判断をしようとしているのか」を共有する。
- 四半期ごとの進捗レビュー: 中期計画や目標に対して、定期的に振り返りを行う。状況に応じて軌道修正が必要であれば、その理由をきちんと説明し、関係者の理解を得る。
- 部門横断チームの活用: 大きなプロジェクトや新製品開発などでは、部門を超えたチームを作り、経営と現場双方の情報を集約する。こうすることで、社長の意図や考えをより早い段階でチームが理解し、現場のリアルを経営者に伝えられる。
このような仕組みを整えていないと、どうしても「社長の鶴の一声」で全てが進んでしまいがちです。組織としての納得感を醸成するためにも、情報共有と合意形成の場をきちんと設定することが肝要です。
人材育成と権限委譲
中堅中小企業において、社長が方針を頻繁に変えるのは、「全ての意思決定を社長自身が行わなければならない」状態に陥っている場合も多いです。社員や管理職が自ら考え、判断し、動くという仕組みが十分に育っていないため、社長がトップダウンで決めざるを得ないのです。
こうした状況を打破するには、人材育成と権限委譲が不可欠です。社長の視点やノウハウを幹部陣や管理職に段階的に伝授し、経営陣の「分身」として意思決定を任せられる人材を増やしていくのです。例えば、若手のリーダー候補を外部研修に派遣したり、社内でミニ・プロジェクトを任せて成功体験を積ませたりすることが考えられます。
権限が委譲されれば、社員も「社長がなんでそこまで細かく指示するんだろう」と思わなくて済みますし、社長も「自分が全部コントロールしなくても、組織が動く」という安心感を得られます。その結果、方針のブレが減り、経営者の判断がより大局的・戦略的になっていきます。
組織文化(カルチャー)の確立
最後に挙げたいのが「組織文化(カルチャー)の確立」です。これは非常に抽象度の高い話ですが、組織風土そのものが「チャレンジを奨励する」「変化に対して前向き」「情報共有を大切にする」という性質を持っていれば、多少の方針変更があっても大きな混乱なく対応できるようになります。
一方、閉鎖的で上下関係が厳しく、情報が上から下へ一方向にしか流れない組織では、経営者の意図を汲み取ることも、現場の声を経営に届けることも難しくなります。これでは、視座のギャップが大きくなるばかりです。
「組織は文化で動く」と言われるように、経営者自身がオープンコミュニケーションを励行し、「どんな意見でもまずは受け止める」という姿勢を示すことが重要です。これが経営陣から管理職、さらに一般社員へと浸透していけば、たとえ経営環境が変わり社長が新たな方針を打ち出したとしても、「なぜ今これにチャレンジするのか」がスムーズに伝わりやすくなります。
Q&A
Q1. 社長が頻繁に方針を変えても、現場が混乱しないようにするにはどうすればいいでしょうか?
A. まずは、方針が変わる理由や背景をしっかり説明する機会を設けることです。定期的なミーティングや情報共有の仕組みを整え、「なぜその方針が必要なのか」を論理的に伝えましょう。その際、できれば中期計画や会社のビジョンと結びつけて話すと、社員の納得度が高まります。
Q2. 経営者としては現場目線に立ちたいのですが、時間的にもなかなか難しく、どこから手を付ければいいのかわかりません。
A. まずは日常のコミュニケーションの質と量を見直すのが第一歩です。週に一度でもいいので、部門やキーパーソンとの短いミーティングを設け、彼らの悩みや進捗を聞き出しましょう。また、時には実際に現場へ足を運び、五感で現状を把握するのも有効です。経営者が現場に顔を出すだけで、社員は大きく意識を変えるものです。
Q3. 経営理念やビジョンを示しても、実際に行動に移してもらえないケースがあります。どうしたら理念を“活きたもの”にできますか?
A. 理念やビジョンを具現化するためには、具体的な行動指針や評価制度に落とし込む必要があります。たとえば「お客さま第一主義」を掲げているなら、顧客満足度を定量的に測る仕組みを作る、優れた顧客対応をした社員を表彰するなど、日常行動の中に理念を組み込みましょう。理念を掲げるだけでは浸透しません。“行動レベル”まで落とし込み、成果をチェックし、フィードバックするプロセスが欠かせません。
Q4. 人材育成や権限委譲を進めたいのですが、どうしても失敗を恐れてしまい、社長があれこれ口を出してしまいます。
A. 失敗を恐れる気持ちはよくわかりますが、社員が成長するにはある程度の“任せる覚悟”が必要です。小さなプロジェクトや比較的リスクが小さい業務からスタートし、成功体験と失敗の学びを積ませるのがセオリーです。ポイントは、失敗を責めずに「なぜ失敗したのか、次はどうすればいいのか」を一緒に考える文化をつくること。これにより、社員の自走力が徐々に育まれ、社長の負担も軽減されていきます。
Q5. 組織カルチャーを変えるにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
A. 組織カルチャーは一朝一夕には変わりません。数年単位の取り組みが必要です。とはいえ、経営者が強い意志をもってオープンコミュニケーションを実践し、管理職の行動指針や評価制度などの“制度面”を整備すれば、1〜2年ほどで徐々に変化を感じられるケースもあります。最も重要なのは継続的な取り組みと、経営者自身が“体現者”になることです。口先だけでなく、「社長が自ら動いて示す」姿勢がカルチャーをつくっていきます。
まとめ:組織の未来を左右する“叱り方”を見直そう
ここまで、「社長が方針をコロコロ変える理由」と「視座のギャップを埋める方法」について解説してきました。改めてポイントを整理すると、以下のようになります。
- 方針の頻繁な変更の背景
- 経営環境の変化に対して、中小企業では過度に反応せざるを得ない構造がある。
- 社長の経験不足や視座の不足、コミュニケーション不足が“方針コロコロ”の原因になりやすい。
- 視座のギャップが問題を複雑化
- 経営者は大局的・長期的視点、現場は目先の業務に注力。
- 経営理念・戦略の全社共有や多様なステークホルダー対応の情報が不十分なままだと、社内外の理解を得にくい。
- ギャップを埋めるための具体策
- 経営理念・中期計画の共有: “なぜ今この施策が必要か”を社内で共有し、納得度を高める。
- リーダーシップと現場連携: 社長自身が現場の声を拾い上げ、リアルな状況を理解する姿勢が大切。
- 定期的な情報共有と合意形成: 週次・月次ミーティングや四半期レビューを活用し、方針変更の理由を明確に伝える。
- 人材育成と権限委譲: 社長が全てを決めるのではなく、組織として自走できる体制を作る。
- 組織カルチャーの確立: オープンコミュニケーションや評価制度を通じて、変化への適応力を高める文化を醸成する。
企業が成長していくうえで、経営者自身の視点の高さや柔軟性が求められるのは事実です。しかし、それを実行する組織が社長の考えを理解し、納得し、主体的に動かなければ成果は出ません。逆に、経営者がいくら先見性を持っていても、社内がついていかなければ方針は空回りするだけです。
今回ご紹介したアプローチは、その「橋渡し」を具体的に進めるうえで有効なものばかりです。中堅中小企業だからこそ、組織としてまとまるスピードや変化対応力は大企業に負けない強みが発揮できるはずです。ぜひ「視座のギャップ」を意識し、経営者と現場が同じ方向を見られる組織づくりを進めてみてください。その先には、方針のブレが減り、生産性や士気が向上した強い組織が必ず待っています。
本コラムがお役に立ち、現場の皆さんが「社長の考えがよくわかるようになった!」と感じられる一助となれば幸いです。経営コンサルタントとしての経験から申し上げると、このような組織改革は一朝一夕で終わるものではありません。しかし、経営者自身が本気で取り組むと決めれば、必ず道は開けます。どうかあきらめずに、粘り強く実践を続けていただければと思います。
私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。


経営者が抱える経営課題に関する
分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。
初回のご相談は1時間無料です。
LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)
音声で聞く”唐澤智哉の「明日が変わる経営ラジオ」~社長が動く瞬間~”も随時更新中!!