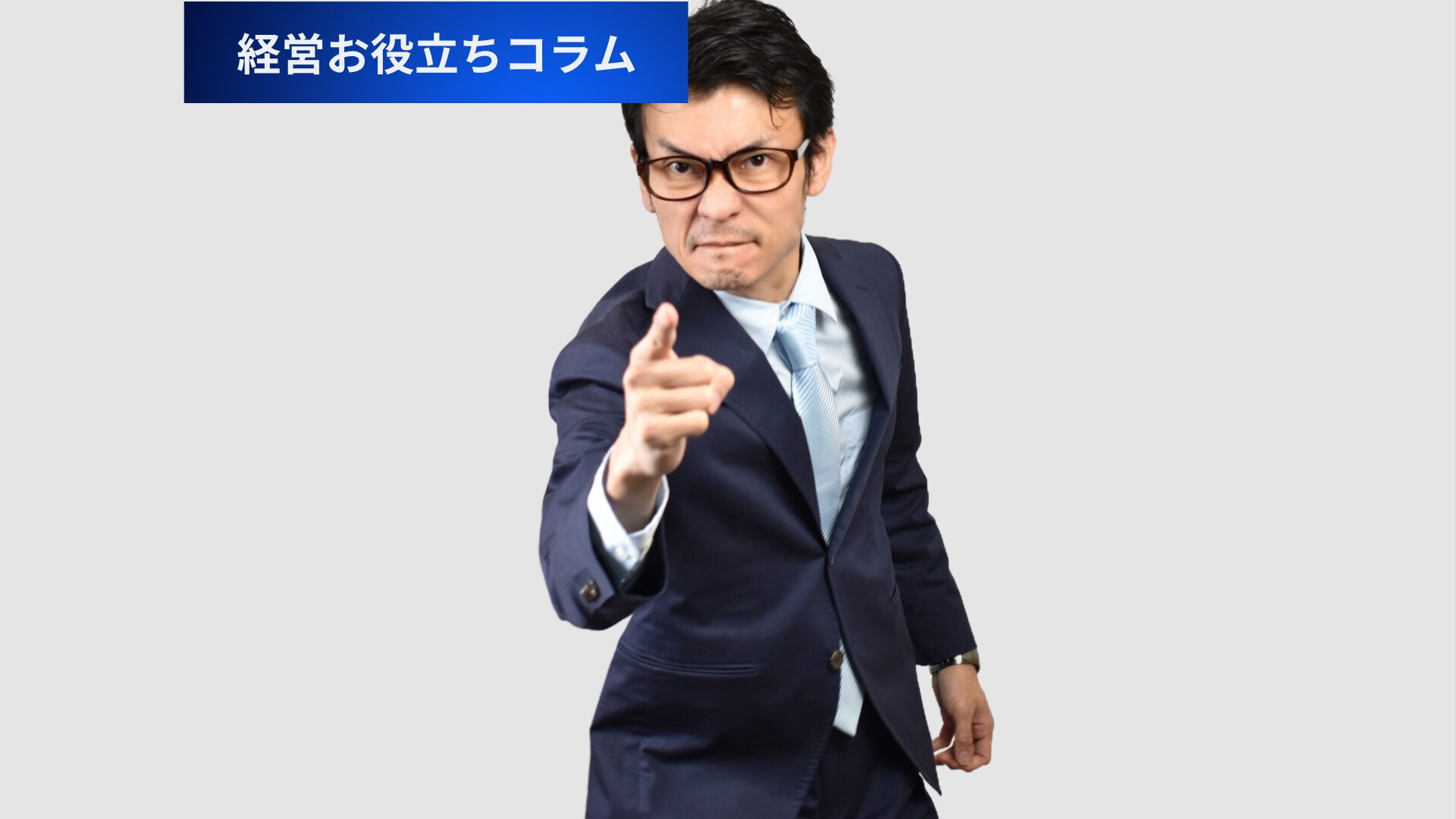唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。
このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。
あなたの組織には、いわゆる「決めつける人」はいませんか?
例えば、会議の場で「〇〇は絶対にこうなるから……」「どうせあの部署は何をやっても変わらないよ」といった言葉を口にし、周囲の意見や可能性を狭めてしまうタイプです。経営者の方や管理職の方なら、一度はそうした「決めつけ」によって不快な思いをしたり、組織のチームワークを損なってしまった経験があるかもしれません。
私自身、多くの中堅中小企業の経営に関わってきましたが、「決めつける人」が組織に与える影響は少なくありません。
本コラムでは、その深層心理を掘り下げるとともに、具体的な悪影響や対策を考えてみたいと思います。人材不足や激しい競争環境のなかで、社内の人間関係やモチベーションが崩れてしまうと企業の成長は大きく阻害されてしまいます。「決めつける人」を放置すると何が起こるのか、どう対応すればよいのか——。中堅中小企業の経営者・役員の方々にとって少しでも有益な視点となることを願っています。




「決めつける人」とは何者か?


「決めつける人」の特徴
「決めつける人」とは、物事や人を一面的にとらえ、「こうに違いない」「どうせこうなる」「あの人はいつもダメだ」といった思考パターンに陥りやすい人物を指します。こうした人物は、相手に反論されたり、新たな情報を与えられたりしても、自分の思い込みを修正することが難しいという特徴を持ちます。
- 断定的な言動
「これは間違いなくこうだ」「絶対にダメだ」等といった言い回しが多い点が特徴的です。周囲にとっては「そこまで言い切るのか……」という圧を感じさせ、チームの自由な議論を妨げます。 - ステレオタイプや固定観念への依存
「若い人は粘りがない」「ベテランは頭が固い」など、特定の属性・経験に基づいて物事を画一的に評価しがちです。本人に悪意はなくても、結果として偏見や差別を助長してしまうことが多いです。 - 他者の成長や変化に対する無関心
「どうせあいつは変わらないよ」等のように、相手の未来の可能性を認めようとしません。メンバーが新しいスキルを身につけようとしても、「結局あの人はこうだから」と否定的にとらえてしまいます。
「決めつける人」の深層心理
なぜ「決めつける人」はそのような言動をとるのでしょうか?その背景には、以下のような深層心理が考えられます。
- 自己防衛の欲求
不確実性の高い状況で、人は自分の判断の正当性や安全を確保しようとするものです。簡単に言えば「自分が間違っているのではないか?」という不安から目を背けたいがために、極端な決めつけや断定をするケースがあります。 - 自尊心の維持
「自分は間違いなく正しい」と言い切ることで、周りから「頼りになる」「よく知っている人」という評価を得たいという欲求があります。マズローの欲求5段階説※でいう“承認欲求”や“自尊の欲求”が過剰に働いているとも解釈できるでしょう。 ※人間の欲求を5段階に分類した理論 - 過去の成功体験への固執
過去に「決めつけ」がうまくいった経験や、強いリーダーシップが評価された経験があると、人はそれを繰り返そうとします。脳科学者の研究によると、人は成功体験を再現しようとするバイアス(認知的偏り)が強いことが確認されています。 - 恐怖や不安の隠蔽
心理学の観点では、過剰な「決めつけ」は裏を返せば「自分が見えていない部分を直視するのが怖い」「変化に対応できないかもしれない」という恐怖や不安から来るともいわれています。
組織に与える悪影響


「決めつける人」が単なる「やっかいな人」で済めばいいのですが、実際には組織全体に深刻な悪影響をもたらすことがあります。その代表例を挙げてみましょう。
悪影響①:イノベーションの阻害
「決めつける人」が会議やディスカッションで「どうせ失敗する」「こんなのやってもムダだ」と発言し続けると、新しいアイデアや挑戦が出にくくなります。誰もが「どうせあの人に否定されるだけだ」と思えば、自然と声を上げなくなり、結果として組織のイノベーションは大幅に制限されます。実際、パーソル創業研究所が実施した「心理的安全性の実態調査」では、心理的安全性が高い職場では、従業員が意見を自由に述べやすく、業務上の相談や質問がしやすい環境が整っていることが明らかになっています。このような環境は、従業員の挑戦意欲を高め、新規事業への関心や取り組みを促進する要因となると考えられます。
心理的安全性については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。
悪影響②:社員のモチベーション低下
「決めつける人」から繰り返し否定された社員は、自身の意欲をそがれ、「どうせ自分なんかが意見しても意味がない」と感じてしまいがちです。その結果、組織全体のエンゲージメントが下がり、生産性まで低下します。
悪影響③:組織風土の硬直化
否定的・断定的な意見を繰り返すことで、組織内の交流や風通しが悪くなり、萎縮した雰囲気が生まれます。このような状態が続くと、部門間の連携は弱まり、果てには対立や派閥争いの火種にもなりかねません。「あの部門はやる気がない」「あのチームは無理だ」などのレッテル張りが広まってしまい、組織が硬直化してしまうのです。
悪影響④:人材育成の停滞
「決めつける人」は部下や後輩の成長を阻害する傾向が強いです。なぜなら、若手や新任スタッフが何か新しいことをやりたい、あるいはミスをしながら学ぼうとしても、すぐに「あなたはどうせできない」「その方法は無駄」と否定してしまうからです。結果として、若手も「どうせ何をやっても否定される」と思い込み、積極性や挑戦心を失っていきます。組織の将来を担う人材が育っていかない状況は、企業の長期的な成長にとって極めて大きな損失となります。






「決めつける人」への具体的アプローチ


面談やコーチングによる自己認識の促進
「決めつける人」は、自分が「決めつけている」という自覚が薄い場合が多いです。そこで、まずは面談やコーチングなど、1対1の場で本人の発言の傾向をフィードバックし、自分自身の言動を客観的に見るプロセスを作りましょう。
- 具体例を挙げてフィードバック
「先日の会議で、Aさんが新規案を出したときに「どうせ無理だ」と返していたが、それによって他のメンバーが意見を言いづらくなっている」というように、具体的に例示して伝えると効果的です。 - 変化するメリットを提示
「あなたがもう少し柔軟なアプローチを取れば、周囲が積極的に意見を出すようになり、最終的にあなた自身の業務もスムーズになる」というように、本人にとってのメリットをわかりやすく提示します。
チーム・ディスカッションのルール化
会議やディスカッションの場で、「否定から入らない」「最初の◯分間はどんな意見も許容する」など、ルールを設定してみるのも有効です。ブレインストーミングの要領で「とにかくアイデアはまず出し切る」フェーズを設けることで、「決めつける人」の発言が抑制されやすくなります。
- ファシリテーターの配置
必ず会議の進行役(ファシリテーター)を置き、意図的に場をコントロールする方法です。ファシリテーターは「決めつける発言をしそうだな」と思ったら、話を横に広げたり他のメンバーに振ったりして、議論の機会を守る役割を担います。
評価指標の見直し
「決めつける人」が周囲を否定してしまう要因として、「否定することで自分が優秀に見える」と考えている場合があります。そこで、人事評価や成果指標を見直し、「周囲の意見を尊重し、建設的な議論を促したかどうか」を評価の一つに入れるのも手段の一つです。
- 建設的なコミュニケーションを評価する制度
たとえば「建設的フィードバック数」や「アイデア提案数」「部下の育成貢献度」といった指標を導入して、否定的なコミュニケーションだけでは評価が上がらないようにする仕組みづくりです。
外部研修や心理学的アプローチ
時には、専門家を招いた研修や外部のコンサルタントが提供するワークショップなどを活用し、「決めつける人」本人のみならずチーム全員のコミュニケーションスタイルを見直す機会を設ける打ち手も有効です。認知バイアスや心理的安全性などの基本的な知識を全員が共有することで、互いの行動を客観的に振り返りやすくなるメリットがあります。
Q&A
Q1. 「決めつける人」に注意をすると余計に関係が悪化しそうで心配です。どうすればいいでしょうか?
A.注意やフィードバックの方法が一方的に「悪いところばかり指摘する」形になると、たしかに関係性が悪化する可能性があります。そこでおすすめなのは、まずは強みの承認から入る方法です。たとえば「あなたの経験や知識が豊富で、チームもその点を頼りにしている。ただ、〇〇という場面でちょっと決めつけが強いように感じられる。そこが改善されると、もっと周りが前向きに動けるようになる」という伝え方です。最初にポジティブな面を評価したうえで、具体的な行動例を示しながら指摘することで、相手の自尊心を傷つけずに変化を促しやすくなります。
Q2. 「決めつける人」が上司の場合、部下や他の社員はどう対応すればいいですか?
A.上司が決めつけ傾向を持っている場合は、部下が単独で対処するのは難しいケースが多いです。まずは信頼できる第三者(人事担当者や別部署の管理職など)に相談し、組織全体として対応策を検討できる体制をつくることが重要です。また、上司に直接フィードバックする場合も、一対一ではなく、上司の上司やファシリテーターを交えたうえで行うなど、安全な環境を整備することがポイントとなります。
Q3. 組織のトップである私自身(経営者)が「決めつけ」傾向を改善したいのですが、どこから手を付けるべきでしょうか?
A.経営者自身がその問題意識をもっているのは、改善への大きな第一歩です。最初に取り組むべきは、自分がどのような場面で「決めつけ」発言をしているか記録し、振り返ることです。会議録や録音を聴き返すのも有効です。そのうえで、信頼できる幹部やコンサルタント、または外部のメンターなどに「自分が決めつけていたら指摘してほしい」と依頼しましょう。自分では気づけない言動のクセが客観的に見えてきます。
Q4. 組織全体の雰囲気を改善したいのですが、具体的な施策は何かありますか?
A.心理的安全性を高めるための活動が効果的です。たとえば「月に1回、全員が自由に意見を言えるオープンディスカッションを設ける」「ダイバーシティ(多様性)に関するワークショップを定期的に開催する」など。ここで大事なのは、経営者や管理職が積極的に参加し、模範的な態度を示すことです。「どんな意見もまずは受け止める」という姿勢をリーダー層が見せることで、徐々に組織全体が柔軟な風土に変わっていきます。
まとめ
「決めつける人」は、本人が思っている以上に組織全体に悪影響を及ぼす存在です。イノベーションの阻害やモチベーションの低下、人材育成の停滞など、中堅中小企業が持つ貴重なリソースを大幅に損なってしまいます。裏を返せば、こうした「決めつけ」を軽減し、多角的な意見を許容する組織文化を育てることは、企業の成長にとって大きなプラスとなります。
- まずは「決めつけ」の存在を認識する
問題を明確化し、それがどのような組織的悪影響を生むかを経営者・管理職を中心に共有することが第一歩です。 - 本人への適切なフィードバックと対策
面談やコーチング、ルール設計によって、“決めつけ”を緩和し、周囲の意欲を引き出す仕組みづくりを進めましょう。 - 組織風土の改善
「決めつける人」を個人の問題だけで終わらせないことが大切です。組織として心理的安全性を高め、多様な意見を歓迎する土壌を作るには、人事評価制度や研修の見直しを含めた取り組みが必要となります。
激しい環境変化が常態化しているいまだからこそ、「どうせ無理」「絶対に変わらない」という発言は、大切なイノベーションや変化の芽を摘んでしまいかねません。
経営者・管理職の皆様が、まずは自社の中で「決めつけ思考」が強い言動や風土がないかをチェックすることで、組織内に潜んだ潜在的リスクを取り除き、新たな活力を呼び込むきっかけとなることを願っています。
長年の経験を踏まえて申し上げると、多くの中堅中小企業が一度「決めつけ風土」に陥ると、経営者が危機感を覚えるまで、ずるずると同じ風土が続いてしまいがちです。逆に、一度「開かれた議論と挑戦を奨励する文化」に転換すれば、それは企業全体に波及し、若手のアイデアが経営を大きく伸ばす原動力になることも少なくありません。
もし「うちの会社でも、あの人が決めつけるタイプで困っている」という状況なら、一度振り返りの場を設けてみてはいかがでしょうか?問題を明確化し、全社的に取り組む第一歩を踏み出すだけでも、組織には新しい風が吹き始めるでしょう。 本コラムが、あなたの会社の組織改革の一助となれば幸いです。
私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。


経営者が抱える経営課題に関する
分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。
初回のご相談は1時間無料です。
LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)